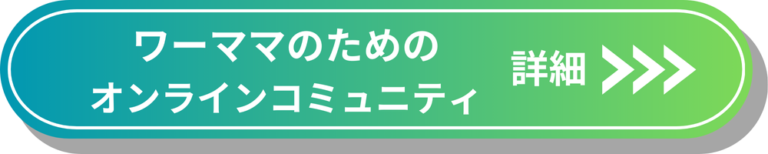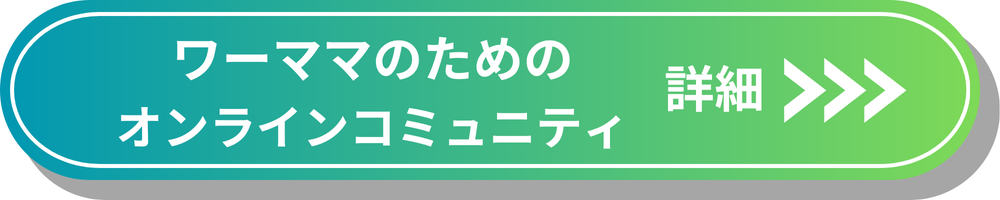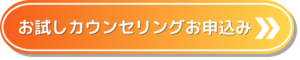はじめまして。
ママの笑顔を引き出すカウンセラー、谷口つくしです。

仕事と育児の両立に悩んでいる方、今後のキャリアについて考えている方、パートナーとの関係に悩んでいる方を中心に、カウンセリングを行っています。
カウンセリングを受ける際、「カウンセラーはどんな人なんだろう?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
また、カウンセリングでは、クライアント様と私(カウンセラー)の相性や信頼関係がとても大切になります。
そこで、私のこれまでの人生を知っていただくことで、カウンセリングに対する不安が少しでも軽くなればと思っています。
少し長い文章になりますが、ぜひお読みいただけると嬉しいです。
目次
・教室の隅で感じた劣等感・・・ 母の存在が前を向かせた少年時代
・選んだ仕事はエンジニア 「家族のため」と激務に耐える日々・・・
・父としての第一歩 「働きづめで、子どもの成長を見逃してませんか?」
・転勤の打診 ライフワークバランスの崩壊が始まる
・将来が見えない 暗澹たる40代
・休職が気づかせてくれた 自分の本当の価値と周りの支え
・自分の天職に出会えた エンジニアから「人」に向き合う仕事へ
・時間と仕事に追われる職場のママ達 家庭と仕事の両立の難しさ・・・
・ママたちが諦めずに生きられる社会へ
・ママは家族のHUB(中心)です いつも笑顔でいて欲しい
・ママの笑顔が家族の幸せをつくる つくしスタイルのカウンセリング
・オンラインコミュニティ 【ママHUB】に込めた思い
教室の隅で感じた劣等感・・・
母の存在が前を向かせた少年時代

僕は両親と妹、弟の5人家族の長男として生まれました。
父は仕事で家を空けることが多く、家庭の中心にはいつも母がいました。
僕は背が低く、引っ込み思案な性格で、教室の隅で皆を眺めるような子どもでした。
スポーツが得意な子、活発な子、自信に満ちた子たちを羨ましく見つめ、下を向きながら家に帰ることが多かったです。
でも、家に帰ると、そこには母がいます。
「つくしには、つくしのいいところがあるんだから。そのままで大丈夫」
母の言葉を聞くと安心し、不思議と「頑張ろう」という気持ちになり、勉強だけでなく、苦手なスポーツにも挑戦していきました。
とはいっても、多感な学生時代はコンプレックスも多く、悩みも尽きません。
それでも、家に帰れば、いつも母の笑顔がありました。
振り返ってみると、今、僕が「困難があっても、上を向いて諦めない」姿勢を持てるのは、母の存在のおかげだったのだと感じます。
母は若くして亡くなってしまいましたが、思い出の中の母が、今も僕を支える原点になっているのかもしれません。
選んだ仕事はエンジニア
「家族のため」と激務に耐える日々・・・

子どもの頃から工作や技術、理科が好きだった私は、大学で電気工学を学びました。
卒業後は電機メーカーに就職し、エンジニアとしての生活が始まります。
しかし、エンジニアの仕事は残業と休日出勤の連続でした。
当時は「男は仕事をして稼いでなんぼ」という価値観が強かった時代。
私自身も「残業代がもらえるから」と自分に言い聞かせるように働き続けました。
そんな中、今の妻と出会います。
彼女は”こんな僕でもいい”と、ありのままの僕を受け入れてくれる存在でした。
当時は「寿退職」(今ではあまり使われない言葉ですが)が一般的で、妻は専業主婦に。
私自身も「男は仕事、女は家庭」といった性別役割分担の価値観に疑問を持つことなく、それが当たり前だと思っていました。
一方で、仕事が中心となる生活スタイルには、どこか違和感を感じることもありました。
しかし、「家族を幸せにするため」という大義名分ができたことで、より一層仕事に打ち込むようになっていきます。
そんな私の価値観を大きく変えたのが、長男の誕生でした。
父としての第一歩
「働きづめで、子どもの成長を見逃してませんか?」

長男誕生時、ちょうど残業が少ない部署にいたおかげで、育児に参加できたのは幸運でした。
妻が退院するまでは、会社に行く前と帰宅後の1日2回病院へ通い、退院後は沐浴が僕の担当です。
最初は赤ちゃんをどう抱けばいいのか分からず、「壊してしまいそう」と緊張の連続。
それでも、恐る恐る抱っこし、背中をトントンしてげっぷを出させてあげられた時は、誇らしい気持ちになったものです。
「子育てって、楽しい♪」
子どもの成長はあっという間で、その一つ一つをかみしめる時間は、何にも代えがたいものでした。
当時は男性の育休制度がなかったため、我が子の成長を間近で見守ることができた自分は、幸せ者だと心から思います。
その一方で、育児は妻任せで、子育ての喜びを知らない男性の多いこと・・・
「我が子の成長を感じる間もなく働くことは、幸せなのか?」という疑問が芽生え始めました。
転勤の打診
ライフワークバランスの崩壊が始まる

40代手前、僕は会社から転勤の内示を受けました。
その部署は転勤を伴い激務であることは分かっていましが、内示を断ることは、すなわち会社を辞めることを意味します。
ちょうどその頃、妻は第二子を妊娠しており、経済的なリスクを負うわけにはいきません。
「僕が家族を支えなきゃ、どうする…」
当時の僕には転職という選択肢はなく、ここから長い苦悩の日々が始まりました。
そんな中、次男が誕生します。
ちょうど長男が小学校に上がるタイミングで、妻は産後体調を崩し、2〜3ヶ月ほど動けない状態でした。
しかし、僕は激務の為、育児に関わる余裕はなく、妻の両親は遠方、僕の母はすでに亡くなっていたので、頼るところがありません。
「夫婦二人じゃ無理だ…」
途方に暮れていたところ、比較的フリーな働き方をしていた義姉がどうにか時間を作り、助けに来てくれました。
このとき初めて、「子育てには支援の手が必要だ」ということを痛感しました。
長男の時は、育児の喜びをしっかり感じられたのに、次男の子育ての記憶はほとんどありません。
長時間残業や休日出勤が続き、わずかな休みも疲れ果てて動けない。
家事や育児はすべて妻に任せきりになり、気づけば子どもの成長を見逃していました。
今振り返ると「あの時、もっと…」と思うことばかり。
それでも、ワンオペながら家庭を明るく支えてくれた妻には、心から感謝しています。
だからこそ、皆さんには後悔のない子育てをしてほしい――そう願っています。
将来が見えない
暗澹たる40代

40代になり、仕事内容が変わったことで、エンジニアとして技術的についていけなくなりました。
必死に食らいつくも、思うように成果は出せず、余裕のない毎日が続きました。
閉塞感に押しつぶされそうになりながらも、僕を支えてくれたのは家族でした。
へとへとになって帰宅すると、家庭の中心には妻がいて、子どもたちも笑顔で迎えてくれる。
その温かさが、僕にとって唯一の救いでした。
家族のために頑張ろう--そう思うことで、なんとか毎日を乗り越えていました。
しかし、また新たな問題が訪れます。
仕事の成果が上がらず、昇給もままならない中、子どもたちの教育費が本格的にかかる時期が近づいてきたのです。
公私ともに追い詰められ、身動きが取れなくなっていた僕を見て、妻が仕事を再開することを決意しました。
こうして、共働きの生活がスタートです。
「男は大黒柱として、稼いでなんぼ」
そんな昔ながらの価値観を抱えていた僕でしたが、自分のプライドを気にしている余裕すらありませんでした。
休職が気づかせてくれた
自分の本当の価値と周りの支え

職場にも仕事内容にも馴染めず、残業は月80時間。
「一家の大黒柱になれない」という自責の念に押しつぶされ、ついに心も身体も限界を迎えました。
僕は会社に行けなくなり、休職へ——。
しかし、この求職期間が、結果的に私の人生の転機となったのです。
苦しみの中で、藁にもすがる思いで、生まれて初めてカウンセリングを受けることになりました。
「男が弱音を吐けるか」といった気持ちもありましたが、安心できるカウンセラーの前だと、自然と素直な気持ちを吐き出せ、抑え込んでいた感情があふれ出します。
「僕は僕のままでいいんだ」——その言葉がすっと心に染み込みました。
自分を苦しめていたのは、「こうあらねば」「こうあるべきだ」の思い込みや価値観だった。
そして、僕は男として一人で戦わなければと思っていたけれど、本当はずっと周りに支えてくれる人がいた。
妻や子どもたちだけでなく、亡き母、実家の家族、妻の家族、友人、上司、同僚……
ただ、僕が気づいていなかっただけだったのです。
また、この頃から、「会社の中だけを見ていてはいけないのかもしれない」と思うようになり、本を読み漁ったり、講演会に足を運ぶようになりました。
20年以上エンジニアとして、機械を相手に仕事をしてきた僕にとって、「人」や「心」と深く関わることは、とても新鮮な体験でした
自分の天職に出会えた
エンジニアから「人」に向き合う仕事へ

カウンセリングをきっかけに心理学を学び、少しずつ気持ちを立て直していきました。
同時に、40代に入り感じていた「エンジニア」という仕事への違和感が、はっきりと形を持ち始めます。
これまで向き合ってきたのは「機械」。
でも、人生の葛藤を経て、僕の興味は「人」へとシフトしていました。
「人を助ける仕事がしたい」
そう考え、配置替えを希望し続け、ついに「人事課」へ異動が決まりました。
エンジニアの仕事には誇りを持っていましたが、苦悩を乗り越えた後に就いた人事の仕事は、まさに「天職」でした。
セミナー開催、個別相談、啓蒙活動、企画運営、労務事務——。
どの業務も「人」と向き合う仕事。
その先にいるのが「人」だと実感できることが、何よりも嬉しく、やりがいを感じました。
人の役に立つのならと、社労士・ファイナンシャルプランナーの資格も取り、仕事に活かしていきました。
そして気づけば、人事としてのキャリアは10年を超えていました。
その間にキャリアカウンセラー・キャリアコンサルタントといった職種も知りました。
もし40代の一番苦しかった時期に、こうした相談できる人に出会っていたら、あの荒んだ気持ちにならずに済んだのではないか、と考えることもありました。
「だからこそ、今度は自分がその役割を担いたい」その決意が、今の僕に繋がっています。
時間と仕事に追われる職場のママ達
家庭と仕事の両立の難しさ・・・

時代は「女性活躍」や「働き方改革」が叫ばれるようになっていました。
そして、私が所属していた人事課は女性9割・男性1割という職場。
そこには、さまざまな家庭の事情を抱えながら働くママたちがいました。
- 乳幼児を抱え、保育園の送迎をするママ
- 部活や習い事の送迎と手がかかる小学生のママ
- 塾などの教育費もかさんでくる思春期中高生のママ
- 学費や仕送りが必要な大学生を支えるママ
そんな中、「子どもが熱を出した」と欠勤や早退をするのは決まって女性ばかり。
男性社員が同じ理由で休むことは、ほとんどありませんでした…
職場でも、働くママたちが「しんどそうだな」と感じることが増えていきました。
できる限り相談にのり、業務負担を軽減できないか試行錯誤しましたが、当時は制度が整っておらず、組織の中で自分一人ができることには限界がありました。
そんな中、仕事と育児の両立に悩み、鬱になってしまった女性社員が辞表を出しました。
彼女は人一倍責任感が強く、仕事にやりがいを持ちながら成長していく、真面目な社員でした。
ゆっくり休職し、再復帰を薦めましたが彼女が言った言葉は
「私、もう、頑張れません……」
彼女が、これ以上頑張れないというほど、頑張ってきたことを僕は知っていました。
僕には、それ以上彼女を引き留める言葉は見つかりませんでした…
「そこまで追い詰められる前に、もっとしてあげれることがあったのでは」と、自問自答する日々でした。
ママたちが諦めずに生きられる社会へ

働くママたちには、それぞれの人生や夢、希望があるはずです。
- 子どもとの時間を大切にしたい
- 家族とゆっくり食卓を囲みたい
- 自分の趣味や好きなことに時間を使いたい
- 夫との関係や育児・家事のバランスを整えたい
- キャリアを積み、成長し続けたい
- 自分のやりたい仕事で収入を得たい
- 「ママだから」と諦めず、自分らしい生き方をしたい
それなのに、社会の仕組みや役割意識のせいで、何かを諦めたり、自分を犠牲にする人が多いのも事実。
そんな現実を目の当たりにし、僕は彼女たちを応援したいと思うようになりました。
「家族も大事にしながら、自分の人生も大切にしてほしい」
その想いが、自分の進む道を決めました。
会社員生活に終わりを告げた僕は、カウンセラー&キャリアコンサルタントとして、新たなスタートを切ることにしました。
ママは家族のHUB(中心)です
いつも笑顔でいて欲しい

私は、二人の「母(ママ)」を知っています。
ひとりは、私を産み育ててくれた母。
もうひとりは、私の人生の伴侶であり、息子たちの母である妻です。
ママの笑顔が、家庭の温もりをつくる。
それは、私が育った家族でも、今の家族でも変わらないことでした。
時代とともに男女の役割は変化していますが、ママが元気でいることが、家族全体の幸せにつながることは、今も変わりません。
でも、ママだって悩むし、疲れる。
育児・家事・仕事…ママは毎日、たくさんのことを抱えています。
でも、それを「私がやらなきゃ」と一人で背負い込んでしまうことも少なくありません。
「もう頑張れない」「笑顔になれない」
そんなふうに感じているママは、決して少なくないのです。
だからこそ、 ひとりで抱え込まずに安心して話せる場が必要 です。
ママの笑顔が家族の幸せをつくる
つくしスタイルのカウンセリング

進学・就職・結婚・出産・子育て——
女性の人生には、次々と大きなライフイベントが訪れます。
そんな中で、ママが疲れてしまうと、家族全体が停滞ムードに。
でも、ママが元気で笑顔でいれば、家族にはハッピーな空気が広がります。
だからこそ、まずは ママ自身がハッピーに、笑顔になってください。
つくしスタイルのカウンセリングでは、以下のアプローチを通して、ママが安心して笑顔を取り戻せるようサポート します。
✓安心の土台を作るワーク
✓ 自信を築くワーク
✓ 不安とイライラを解消するワーク
✓ 解決志向ブリーフセラピー 等々
日々の不安や生きづらさから解放され、「ママだから」ではなく「私らしく」生きる ためのお手伝いをします。
どうか、一人で抱え込まずに、まずはご相談ください。
あなたが笑顔になれば、きっと家族も笑顔になれます。

オンラインコミュニティ
【ママHUB】に込めた思い

また、働くママさんを対象とした、オンラインコミュニティ【ママHUB】も主催しております。
「HUB(ハブ)」には、“つながりの中心”という意味があります。
飛行機の乗り換え地点を「ハブ空港」と呼ぶように、たくさんの人や情報が集まり、新しいつながりや可能性が生まれる場所です。
私たちのコミュニティ 【ママHUB】 も、働くママたちが集まり、お互いに支え合いながら成長できる「大事な中心」となる場所を目指しています。
仕事、家庭、育児…さまざまな役割を持つママたちが、ここでつながり、新しい気づきや希望を見つけることができる。そんな温かく力強いコミュニティを一緒に育てていきましょう。